

岡山大学における地域活性化の実践的アプローチと未来デザインの取り組み
岡山大学の未来デザインと地域連携
2025年7月16日、岡山大学で行われた「2024年度岡山大学SDGs推進表彰」の受賞者による取り組み発表会。今回のイベントでは、吉川幸准教授が「地域の未来デザイン(実践編)」について語りました。このプログラムは、岡山大学と国立の4大学の学生が共同で実施するフィールドワークを含む実践型社会連携教育です。
地域に根差したフィールドワークの重要性
吉川准教授が担当するこのプログラムは、人口減少が進む地方の課題を探求するものです。参加学生たちは、授業を通じて問いを立て、その解決策を考えるプロセスを経験します。実践編は2泊3日の合宿形式で行われ、観光客という視点から地域を再評価する活動や、地域の年配者からの話を聞く「温故知新」の試みが含まれています。さらに、岡山県立井原高校の生徒とのワークショップを通じて、世代を超えた交流を促進しています。
学生たちの意識変革と地域への影響
これらの活動は、学生たちに地域社会の実際の姿を見せる機会を提供します。フィールドワークを通じて、地域住民との対話や体験を重ねることで、参加者の意識には顕著な変化が見られました。特に、地域の特性や課題を具体的に理解し、それに対する社会的責任を感じるようになることが目的です。吉川准教授は「学生たちが地域の未来を担う存在となることを期待しています」と述べています。
那須保友学長の期待
発表の後、那須保友学長は参加した学生の進路について質問し、彼らが将来地域社会でどのように貢献していくかに興味を示しました。「学生の成長を見守っていきたい」と語る学長の言葉には、岡山大学が地域中核・特色ある研究大学としての役割を果たすことへの強い期待が込められています。
結論
岡山大学が進めるこの「地域の未来デザイン(実践編)」の取り組みは、教育と地域活性化を結びつける重要な試みです。地域の課題に取り組むことで、学生たちの意識を変え、未来の地域社会を創造する力を育んでいます。このような教育プログラムが、岡山大学から全国へと波及していくことを願っています。
さらに、岡山大学のウェブサイトでは、SDGs推進に関する詳細やその他の取り組みについて情報を確認することができます。地域の持続可能な発展を考える上で、岡山大学は重要な役割を果たしています。今後の彼らの活動に注目が集まることでしょう。





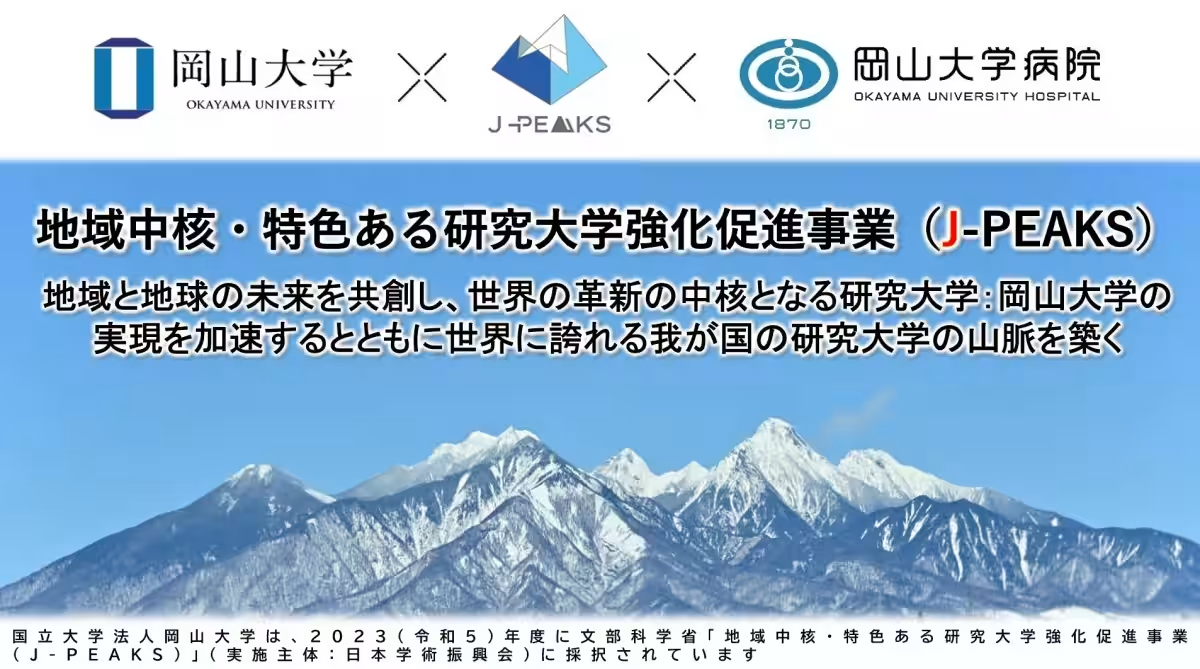


トピックス(イベント)

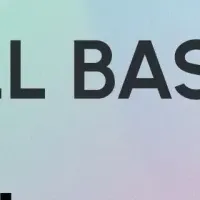
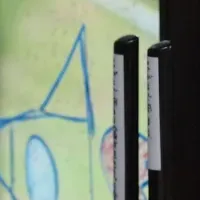





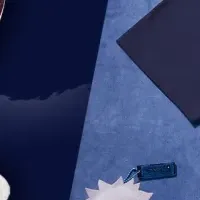

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。