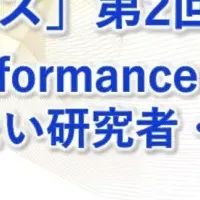

11月11日は鮭の日!サーモン寿司誕生から40周年の魅力を探る
鮭の日:サーモンの魅力を再発見
11月11日は「鮭の日」として、日本記念日協会に認定されています。この日が選ばれた理由は、漢字の「鮭」のつくりが十一を表しているからです。食欲の秋の最中、米や秋刀魚、栗などの収穫と共に、サーモンも旬を迎えるこの日に注目が集まります。
サーモンの歴史と回転寿司の星
サーモンは回転寿司のメニューとして日本中に広まったスターです。1980年代にノルウェーから輸入され、安価で新鮮な養殖サーモンが登場したことが、その普及の大きなきっかけとなりました。特に1992年には、ノルウェーが回転寿司業界にサーモンを提供し始め、瞬く間に人気を博しました。この美しいピンク色と柔らかな食感は広く受け入れられ、日本でのサーモンの消費は拡大を続けています。
養殖技術の進化と地域の特産
日本国内でのサーモンの多くは養殖されており、寄生虫のリスクが低い点が魅力です。最近は、環境に優しい「陸上養殖」が進行中で、地域の特色を活かしたサーモンも続々登場しています。
例えば、青森県の「海峡サーモン」は外海育ちで、冷たい海の影響を受けており、しっかりとした身が特徴です。さらに、「神戸元気サーモン」は酒粕をエサに混ぜており、栄養豊富です。そして、宇都宮市の「うつのみやストロベリーサーモン」や広島の「広島レモンサーモン」なども、地元特産品を活用した新しいブランドとして注目を集めています。
ノルウェー大使館のインタビュー
2025年は日本とノルウェーの外交関係樹立120周年、そしてノルウェーサーモンが日本に上陸して40周年でもあります。ノルウェー大使館の水産参事官、ヨハン・クアルハイム氏に、ノルウェーサーモンの魅力について伺いました。
「1980年代、日本は生食の需要が非常に高かったため、ノルウェーはこの市場を重視しました。回転寿司での成功は大きな転機でした。サーモンは見た目にも美しく、食べやすいため、特に子供たちから人気を集めました。」と彼は語ります。
くら寿司の取り組み
くら寿司では、近年のサーモン人気を受け、日本国内での養殖にも注目しています。特に、函館市での「函館サーモン」と愛媛県の「みかんサーモン」は注目の商品で、それぞれの地域の特産物を活かした新たなサーモンの楽しみ方を提案しています。
養殖技術の革新により、「陸上養殖」も進められ、環境に配慮しつつも高品質なサーモンが供給されています。特に閉鎖循環式システムを利用した養殖方法は、低水温でも養殖が可能であり、持続可能な形での生産が期待されています。
おうちで楽しむサーモンレシピ
くら寿司の商品開発部の中村重男さんによる、おうちで簡単に作れるサーモンレシピも紹介します。たとえば、サーモンのタルタルやサーモンのソテーなど、家庭で楽しむ料理も多彩です。
サーモンのタルタルでは、新鮮なサーモンを使用し、アボカド、オニオンと合わせることで、軽やかな味わいに仕上げます。また、ソテーではじっくりと焼くことでしっとりとした食感を生み出し、焦がしバターをかけて贅沢に楽しむこともできます。
結論
鮭の日を迎える11月11日、サーモンの魅力に触れ、回転寿司の人気メニューとしての歴史を振り返りながら、地域の新たな特産物としての可能性を探る良い機会です。この機会に、ぜひサーモンを味わい、その深い魅力を感じてみてください。










トピックス(グルメ)
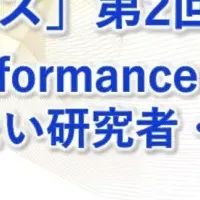
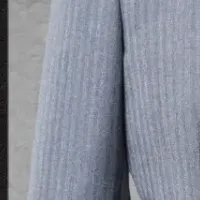

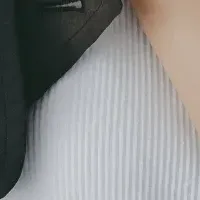


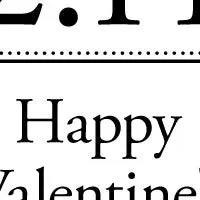
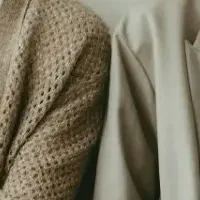

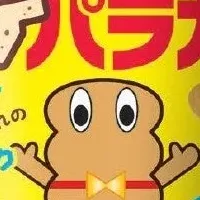
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。