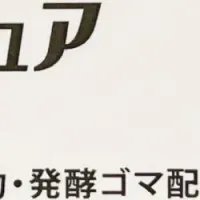

フェリス女学院大学とスズキが進める自動運転車の音のデザイン革新
自動運転車の未来を音でつなぐ
近年、自動運転技術が急速に進化しており、特にレベル4自動運転車の開発が進められています。これに伴い、車両が周囲や乗員に情報を伝えるための方法が重要視されています。フェリス女学院大学の中西宣人准教授とスズキ株式会社の研究チームは、こうした情報伝達を行うための新たな音のデザインについて共同研究を進めてきました。
重要性の高まるサウンドデザイン
自動運転車が進化するにつれ、ドライバーレス車両は自分の動作を周囲に知らせる義務を負っています。ブレーキをかける際や方向転換する時、さらには停車時など、多くのシチュエーションで情報を効果的に伝える必要があります。このようなコミュニケーションを確実に行うために、音による情報伝達が重要です。特に、視覚障がい者や視覚的に不安定な環境にいる人々への配慮が求められます。
中西准教授とスズキの研究チームは、社会のニーズに応じて、報知音のデザインを行ないました。音のデザインには、安全性や親しみやすさ、そして明瞭な情報伝達が求められます。研究チームは、以下の要素に基づいて新たな音を設計しました。
- - 安全性の伝達: 音を聞くだけで危険を察知できることが必要です。
- - 親しみやすさ: 利用者が不安にならないような音を目指しました。
- - 先進性: 新しい技術を象徴するような印象を与えます。
さまざまなシチュエーションへの対応
研究チームは、全8つのシチュエーションに応じた6種類の音パターンを開発し、自動運転車がどのような状態にあるのかを効果的に伝えるための音を設計しました。
- - 自動走行の開始と停止を知らせる音
- - ドアの開閉を知らせる音
- - バス停への停車と発進を知らせる音
- - 緊急停車や臨時停車を知らせる音
さらに、この音が幅広い年代層に均等に伝わるように、プロトタイプの作成と聴取テストを行い、調整を重ねました。
VRを用いた音の評価
新たにデザインされた報知音の有効性を確かめるために、フェリス生と中西准教授のチームは、VRヘッドセットを用いて多様な年齢と性別の被験者に実際に音を体験してもらいました。それぞれの音に対する安心感や危険性、明瞭さ、心地よさを評価しました。この過程は、音のデザインに貢献し、実際の社会に役立つものとなるための重要な一歩です。
実用化に向けた重要な試み
浜松市にて行われた自動運転実証実験「浜松自動運転やらまいかプロジェクト」では、開発の成果が実際の道路で試されました。このプロジェクトは、交通空白地帯における新たな移動手段の提供を目指しており、サウンドデザインはその実用化の鍵となる要素です。
この取り組みを通じて、フェリス女学院大学とスズキは、音による情報伝達がいかにして社会のニーズに応えるのかを示しました。今後、自動運転技術のさらなる発展とともに、多くの人々の安全な移動を支援する音のデザインが進化していくでしょう。



トピックス(その他)
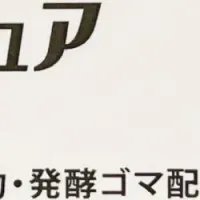
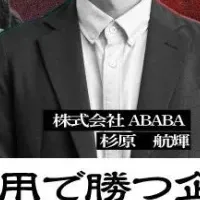








【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。