

岡山大学で生成AIの活用事例を共有する大規模イベントが開催
岡山大学で生成AIの利活用を考える共有会が開催
岡山大学が10月31日に津島キャンパス工学部で行った「OI-Start生成AI活用共有会」には、約130名が集まりました。このイベントは、急速に進化するAI技術を企業でどう活用するかについて、事例や課題を共有することが目的です。後援を受けた岡山県高度情報化推進協議会も関与し、産業界や学術界の垣根を越えた交流が期待されました。
専門家によるインプットトーク
様々な企業からの発表の前に行われたのは、OI-Start会長である野上保之教授の基調講演です。彼は最新のAI技術の発展に言及し、「私たち岡山が持つ地域の個性を大切にしつつ、産業界として何を成し遂げるか考える必要がある」と力強く語りました。これは会場内の参加者にも共鳴し、AIの可能性を感じさせる内容でした。
企業の事例発表
その後、ピープルソフトウェアやトスコを含む7社が自社の生成AI活用事例を発表しました。一例を挙げると、ある企業は深層学習技術を用いて新しいワッペン画像を自動生成する技術を紹介しました。また、生成AI導入に向けたガイドラインの策定過程や独自開発したAIツールの事例なども共有され、参加者の関心を引きました。さらに、デモンストレーションも行われ、参加者は新技術に対する理解を深めました。
学術的視点の提供
学術研究院から門田暁人教授が講演を行い、国内外の生成AIの現状や課題を解説しました。門田教授は特に、ソフトウェア開発における生成AIの活用の将来を展望し、業界の現況にも触れました。この講演も参加者の心をつかみ、多くの質問が挙がりました。
意見交換セッション
イベントの最後には、参加者からリアルタイムで寄せられた質問を受けてのディスカッションが行われました。「生成AIを活用した新しいビジネスモデル」「著作権が絡む問題」といったテーマで活発な議論が交わされました。野上教授は「相互作用を促進させ、岡山ならではの特色を出していくことが大切だ」と締めくくり、参加者に積極的な意見発信を促しました。
今後の展望
生成AI活用共有会は、企業と大学の連携を促進し、岡山地域におけるイノベーションの創出を目指しています。学生からも「こういった勉強の機会は非常にありがたい」との感想が寄せられ、次世代のリーダー育成に寄与する姿勢が見受けられます。今後もOI-Startはこの取り組みを続け、地域にとって新しい価値創造を目指します。
私たちが目指すべきは、技術の進化を地域全体で共有し、岡山をさらに発展させることです。岡山大学の取り組みをぜひ注目していきましょう。












トピックス(イベント)


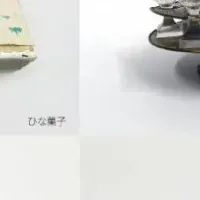



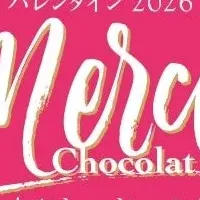
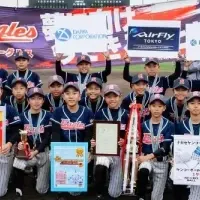


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。