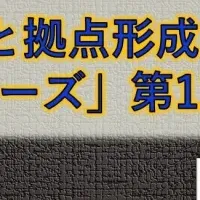
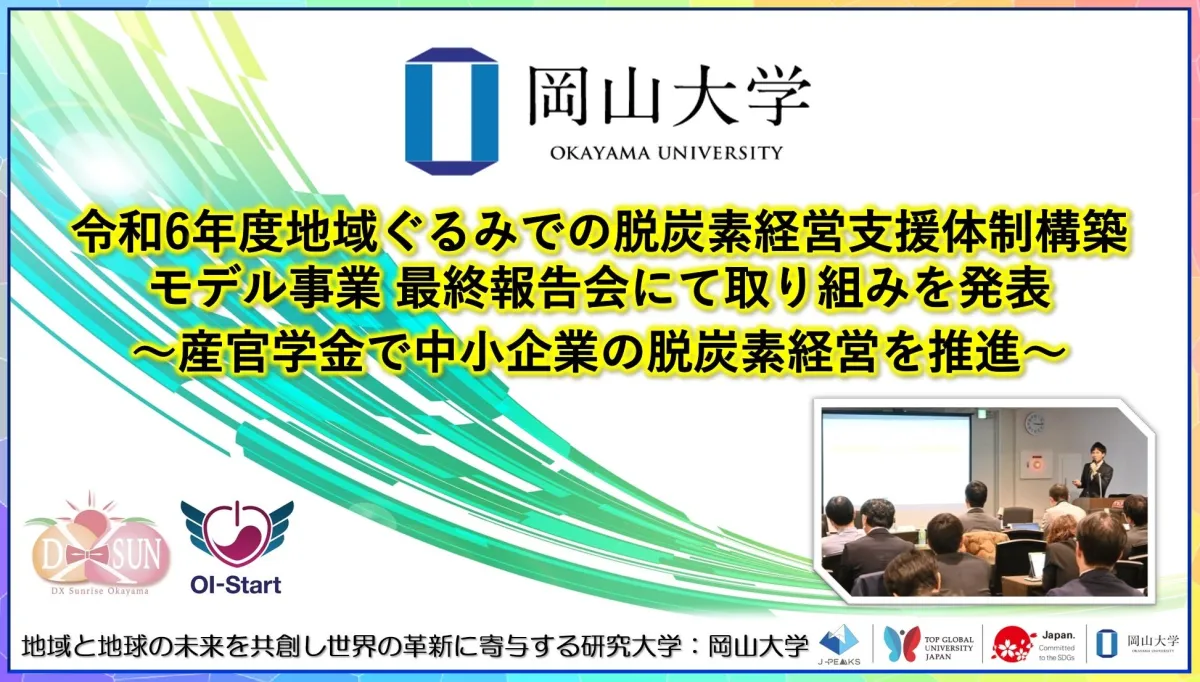
岡山大学が推進する脱炭素経営、地域と連携した挑戦の成果を報告
岡山大学が進める地域脱炭素の全貌
2025年1月29日、岡山大学にて、「令和6年度地域ぐるみでの脱炭素経営支援体制構築モデル事業」の最終報告会が行われました。この事業は、環境省が推進するもので、岡山大学は全国で唯一、大学が代表となって採択されたモデル地域です。実施された活動は地域企業の脱炭素経営の支援を目的としており、学術機関としての取り組みが注目です。
発表された活動成果
当日は、舩倉隆央副本部長がファシリテーターとして登壇し、地域脱炭素創生に向けた「岡山コンソーシアム」の取り組みや、DXやGXに関する支援策について報告しました。具体的には、企業のデジタル変革のビジョン策定を支援するDXサンライズおかやま(DXSUN)との連携が進行中で、カーボンフットプリント(CFP)の算定や温室効果ガスの排出量モデルについても取り組まれています。
学生の成長と環境意識の向上
特に注目すべきは、岡山大学の経済学部が実施している「CO2排出量可視化チャレンジ」です。これは、県内の企業3社を対象に行われ、CO2排出量のモデル算定が実施されました。この成果は地域の企業や支援機関と共有され、これにより企業の脱炭素化を促進するだけでなく、学生たちの環境リテラシー向上にも寄与しています。学生主体の取り組みが地域経済にも好影響をもたらすこの事業は、今後の広がりが期待されます。
パネルディスカッションでの活発な意見
報告会後のパネルディスカッションでは、地域全体での支援方法や中小企業が直面する脱炭素化の課題について、参加者たちが活発な議論を交わしました。舩倉副本部長は、これからも地域社会全体での脱炭素経営支援体制を強化し、学生の参加を増やす体制を整えて、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを進めていく意志を示しました。
岡山大学の未来への展望
昨今、中小企業は日本全体の温室効果ガス排出量の約2割を占める重要な役割を持っており、2050年にカーボンニュートラルを実現するためには、その脱炭素化が不可欠です。岡山大学は、地域金融機関や経済団体と協力しながら、無理なく企業が取り組める脱炭素経営の仕組みを構築していくことを目指しています。
今後も岡山大学は地域と連携し、持続可能な経済の発展に寄与し続けることでしょう。これからの取り組みに大いに期待が寄せられています。持続可能な開発目標(SDGs)とも連携しながら環境問題に対する具体的な姿勢を示す岡山大学のさらなる成長に注目が集まります。
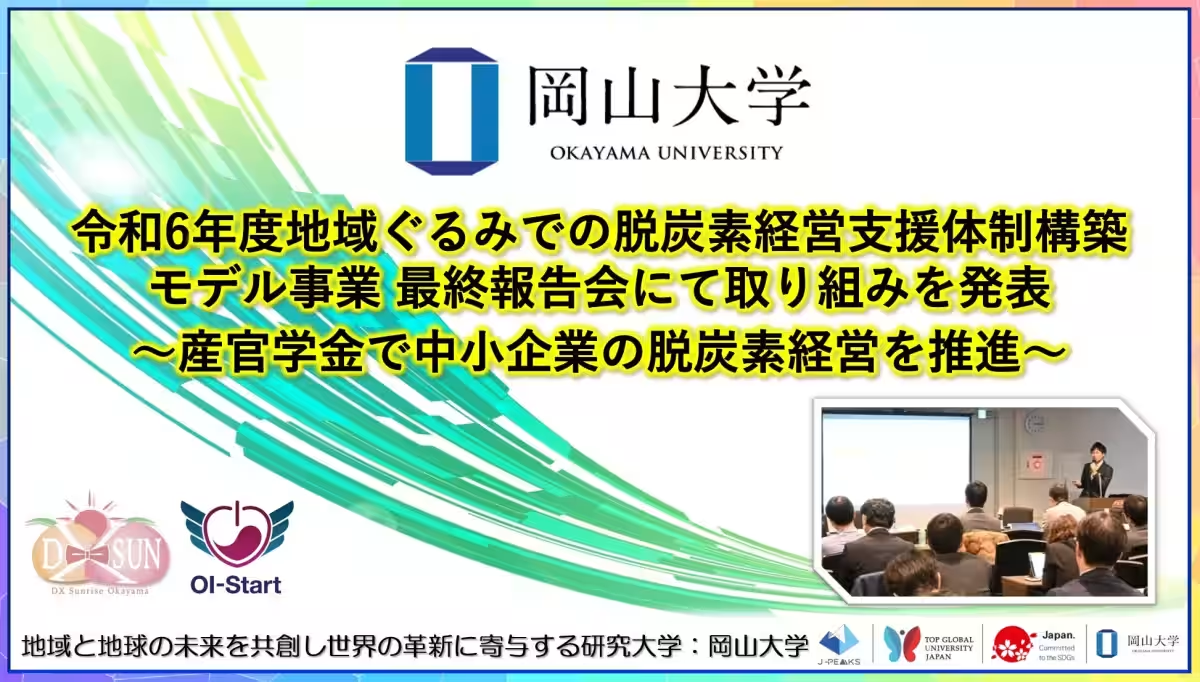





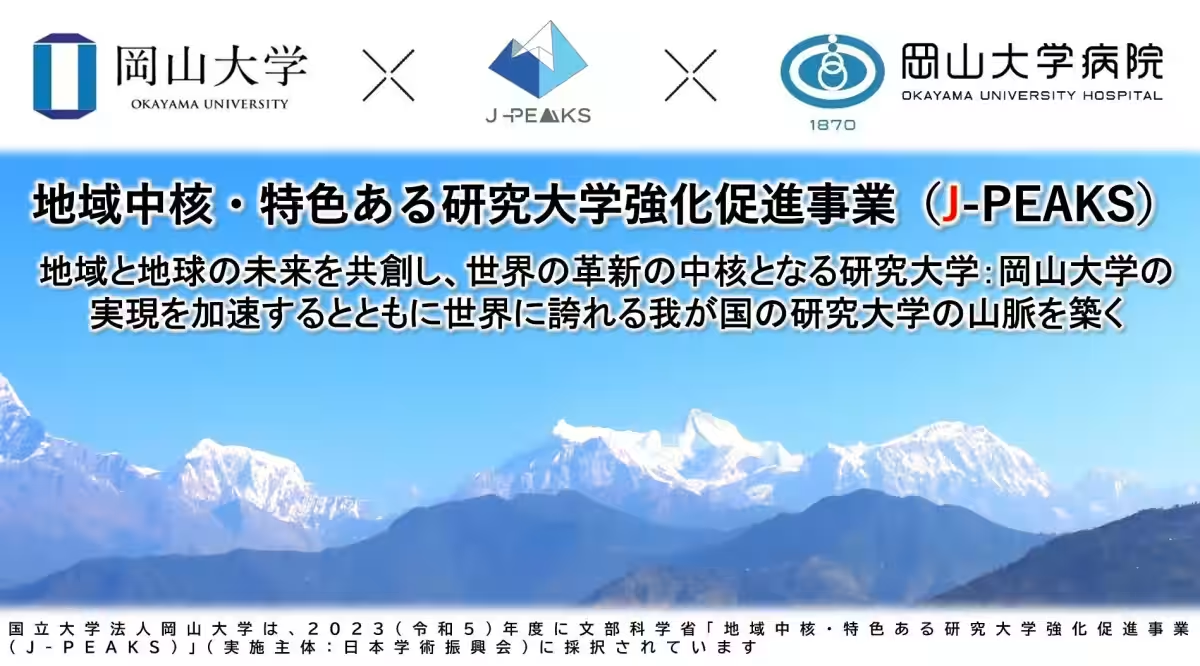


トピックス(その他)
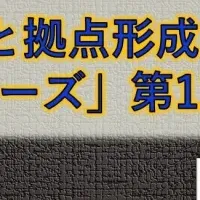
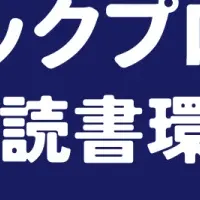
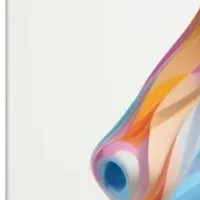

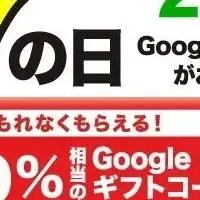



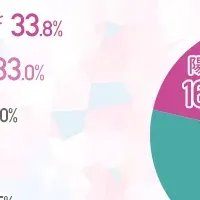
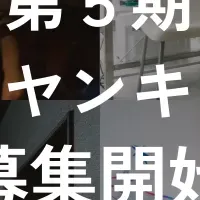
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。