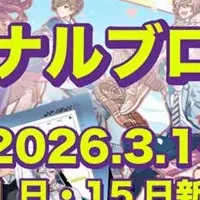

津南醸造が宇宙と日本酒をつなぐ新たな挑戦「スマート醸造」
津南醸造株式会社は、2025年10月7日にパシフィコ横浜ノースで開催された「Design Solution Forum 2025」に登壇し、生成AIを活用した日本酒製造の革新を紹介しました。このフォーラムは、テクノロジーとエンジニアリングをテーマにしたイベントで、津南醸造が伝統的な日本酒の製造方法を現代技術でアップデートする様子が語られました。
代表取締役の鈴木健吾氏が語った講演のタイトルは「日本酒の伝統を生成AIでアップデートする『スマート醸造』」。特に注目されたのは、以下の三つの観点からのアプローチです。
講演の中で鈴木氏は、杜氏や蔵人の長年の経験と、科学的データである発酵データや香気成分を生成AIが統合し、最適な醸造条件を提案するシステムを紹介しました。特に、新潟の「魚沼産コシヒカリ」という地域特有の米を使用することで、より良い酒造りに寄与しています。
「スマート醸造」は、酒造りの効率を向上させるだけでなく、日本酒の副産物である酒粕をナノ粒子素材や半導体材料へと転用するプロジェクトにも応用されています。この「日本酒アップサイクルプロジェクト」において、AIは素材分析やプロセス設計をサポートし、地方発の循環型産業モデルを創造しています。
また、津南醸造が紹介したのは、宇宙における発酵実証プロジェクトでした。これには、月面での醸造や小型衛星での微細藻類培養実験が含まれています。AIは宇宙空間での発酵条件の設計を支援し、将来の「月面酒蔵2040計画」の実現に向けたビジョンを形成しています。
鈴木氏は、「AIは人間の代替ではなく、日本酒の可能性を拡張する共創パートナーです」と述べ、地域資源と発酵技術、生成AIを融合させることで、日本酒が未来の産業基盤を形成できると強調しました。
「Design Solution Forum」は毎年開催される技術フォーラムで、「創ろう、拡げよう、設計者ネットワーク」をテーマに、幅広い分野の専門家が集まり、産業の未来についてのアイデアを交換します。公式サイトでは、さらなるイベント情報が提供されています。
津南醸造は、スマート醸造の技術を日本国内外の蔵元や発酵食品メーカーと共有し、共同研究やAI共創型の地域産業モデルの確立に取り組む意向を示しています。また、日本酒の製造プロセスの利活用の拡大や高付加価値化に挑戦し、宇宙醸造やナノ素材研究など、次世代の発酵の可能性を追求していく予定です。
津南醸造株式会社は新潟県中魚沼郡津南町に位置し、豪雪地帯に根ざす日本酒の生産者です。ここでは自然との共生を大切にし、標高2,000m級の山々からの天然水を仕込み水とし、地元産の「五百万石」や「魚沼産コシヒカリ」を使用して日本酒を醸造しています。近年では品質の向上が顕著で、2025年には「越後流酒造技術選手権大会」で新潟県知事賞を受賞するなど、その技術力が評価されています。
公式ウェブサイトでは、津南醸造の取り組みや製品情報を詳しく知ることができます。



代表取締役の鈴木健吾氏が語った講演のタイトルは「日本酒の伝統を生成AIでアップデートする『スマート醸造』」。特に注目されたのは、以下の三つの観点からのアプローチです。
伝統とAIの融合
講演の中で鈴木氏は、杜氏や蔵人の長年の経験と、科学的データである発酵データや香気成分を生成AIが統合し、最適な醸造条件を提案するシステムを紹介しました。特に、新潟の「魚沼産コシヒカリ」という地域特有の米を使用することで、より良い酒造りに寄与しています。
酒造りの高度化とサステナビリティ
「スマート醸造」は、酒造りの効率を向上させるだけでなく、日本酒の副産物である酒粕をナノ粒子素材や半導体材料へと転用するプロジェクトにも応用されています。この「日本酒アップサイクルプロジェクト」において、AIは素材分析やプロセス設計をサポートし、地方発の循環型産業モデルを創造しています。
宇宙 × 発酵技術への展開
また、津南醸造が紹介したのは、宇宙における発酵実証プロジェクトでした。これには、月面での醸造や小型衛星での微細藻類培養実験が含まれています。AIは宇宙空間での発酵条件の設計を支援し、将来の「月面酒蔵2040計画」の実現に向けたビジョンを形成しています。
津南醸造代表の思い
鈴木氏は、「AIは人間の代替ではなく、日本酒の可能性を拡張する共創パートナーです」と述べ、地域資源と発酵技術、生成AIを融合させることで、日本酒が未来の産業基盤を形成できると強調しました。
Design Solution Forumとは
「Design Solution Forum」は毎年開催される技術フォーラムで、「創ろう、拡げよう、設計者ネットワーク」をテーマに、幅広い分野の専門家が集まり、産業の未来についてのアイデアを交換します。公式サイトでは、さらなるイベント情報が提供されています。
今後の展望
津南醸造は、スマート醸造の技術を日本国内外の蔵元や発酵食品メーカーと共有し、共同研究やAI共創型の地域産業モデルの確立に取り組む意向を示しています。また、日本酒の製造プロセスの利活用の拡大や高付加価値化に挑戦し、宇宙醸造やナノ素材研究など、次世代の発酵の可能性を追求していく予定です。
津南醸造の紹介
津南醸造株式会社は新潟県中魚沼郡津南町に位置し、豪雪地帯に根ざす日本酒の生産者です。ここでは自然との共生を大切にし、標高2,000m級の山々からの天然水を仕込み水とし、地元産の「五百万石」や「魚沼産コシヒカリ」を使用して日本酒を醸造しています。近年では品質の向上が顕著で、2025年には「越後流酒造技術選手権大会」で新潟県知事賞を受賞するなど、その技術力が評価されています。
公式ウェブサイトでは、津南醸造の取り組みや製品情報を詳しく知ることができます。



トピックス(その他)
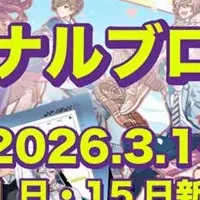
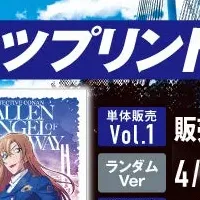
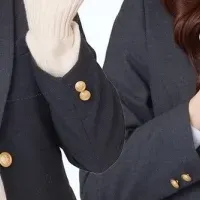

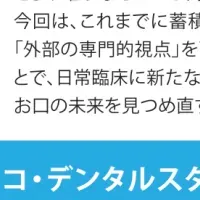





【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。