

次世代モビリティの未来に向けた新たな研究発表と取り組み
次世代モビリティの開発に向けて
株式会社小野測器(代表取締役社長 大越 祐史)は、2025年11月19日(水)に東京大学柏キャンパスで、同大学との共同研究の成果を発表しました。この取り組みは、2022年に始まった「電気自動車の振動計測制御に関する社会連携講座」というもので、今後の自動車産業における重要な進展を期待されています。
共同研究の背景と目的
この社会連携講座は、環境に優しい快適な電気自動車社会を実現することを目指しており、電気自動車の駆動モータに焦点を当てた研究を行っています。特に、車両の振動を抑制し、乗り心地を向上させることが主な目的です。講座の設立以来、研究が着実に進められ、成果も見えてきました。
第1期活動の成果
第1期は2022年から2026年までの活動期間で、平行軸e-Axleを搭載した車両を使用し、振動抑制制御の研究が行われてきました。この研究では、東京大学の藤本博志教授の指導のもと、実際の試験装置を駆使して成果を上げてきました。特に、柏キャンパスに設置された「RC-S 実車トランジェントベンチ」を使用した実験が行われ、実用可能なデータが得られています。
第2期活動の展望
2026年からスタートする第2期においては、これまでの振動抑制研究を継続しつつ、新たに自動車用試験装置の制御技術に関する開発を予定しています。小野測器が愛知県豊田市に建設中の「中部リンケージコモンズ」では、高度な制御技術を持つ試験装置を設置し、自動車業界における先端技術の開発に寄与する計画です。
研究の意義
この講座の設立は、単なる試験装置の開発に留まらず、次世代モビリティ全体にまで視野を広げた重要な取り組みです。電気自動車に留まらず、ドローンや空飛ぶクルマ「eVTOL」など、さまざまな新しい交通手段の開発にも貢献することが期待されています。小野測器は、持続可能な社会の実現を目指し、今後も研究を推進していく姿勢を示しています。
未来に向けた取り組み
小野測器は、地域社会とのつながりを重視し、地元の子どもたちとの交流や清掃活動なども積極的に行っています。これにより、次世代を担うエンジニアの育成や、地域との共生を実現していくことにも力を入れています。電気自動車に関する研究成果は、今後のモビリティ社会の発展に向けた重要なステップとなるでしょう。今後も目が離せません。



トピックス(その他)




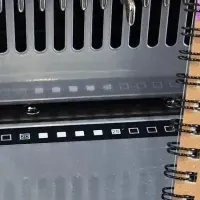





【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。