

次世代モビリティ社会実現へ向けた新しい取り組みが始まる
次世代モビリティ社会実現へ向けた新しい取り組み
2025年10月30日から11月9日まで、東京ビッグサイトで開催される「ジャパンモビリティショー2025」。このイベントに、株式会社トノックス、nicomobi株式会社、株式会社REDERの3社が出展します。展示のテーマは、再生可能エネルギーと次世代モビリティによって支えられる、「誰もが困らない社会」の実現です。日本社会が直面している人口減少や高齢化、インフラの老朽化、労働力不足といったさまざまな課題に対して、技術の革新と社会への実装を通じて持続可能な地域インフラの構築が目指されています。
トノックスの取り組み
トノックスは1950年に設立された車体製造のパイオニアで、神奈川県を拠点とし、軽自動車からバス・トラックまで幅広い車両を生産しています。自社内で設計から製造までを行うことができ、その生産体制は業界で高く評価されています。特に、車体製造における社員の技術力を最大限に引き出す文化が、他にはない魅力的な製品を生み出しています。今後も、この「人財力」を基盤としたイノベーションを通じて、モビリティ社会の発展に寄与することを目指しています。
nicomobiのビジョン
nicomobiは2024年に設立された新しい会社で、超小型EVをビジネス向けに提供することを目指しています。これまでの実績として、ラストワンマイル配送のための実証実験を経て超小型EV技術組合を設立しました。さらに、新たな運用テストでは、過去のモデルを超える性能を確認し、実際の公道でも運用が開始される予定です。人とモビリティの新しい関係を築くために、環境に優しい製品開発に力を注いでいます。
REDERのエネルギーイノベーション
REDERは再生可能エネルギーの普及を目指す企業で、特に伴走型PPA支援事業に特化しています。2050年までの完全脱炭素化を目指し、急速に変化する社会において新しいエネルギー供給形態の構築に挑戦しています。REDERは太陽光発電と蓄電池を利用したエネルギー管理システムの開発を進め、地域の事業継続計画の強化を図るためのソリューションを提供しています。
共創による持続可能な「まちづくり」
日本が抱える構造的な課題への対策として、3社はそれぞれの強みを融合し、新たな地域インフラを推進します。例えば、マイクロユーティリティビークルといえる超小型EV「クロスケ」は、小規模配送に最適化されており、環境配慮型の選択肢として注目されています。加えて、利便性と環境負荷軽減を両立した「そらまる」という取り組みも、古い軽トラックを電気自動車に再生させることで、持続可能な地域の交通手段として期待されています。
新たなエネルギー活用の可能性
また、離島や中山間地域でのエネルギー供給に関するモデルとして、地産地消の再生可能エネルギーを地域内で利用する仕組みも展示されます。太陽光から得た電力を可搬型の蓄電池に蓄え、必要な場所に運搬して使用する点が特徴です。これにより、地域全体で発電した電力をシェアし、バックアップ電源としての機能を持つネットワークが形成されます。
3社共同の未来展望
3社は共に、社会課題の解決に向けた共創の重要性を強調しています。トノックスの社長は、これまでの知見を生かした取り組みの一つであると述べ、nicomobiの社長は「電気自動車だからできること」に焦点を当てた製品開発の方向性を示しました。REDERの社長は、事業推進支援を通じて新しいエネルギー・モビリティ社会の構築を目指していると述べ、未来に向けた展望を明らかにしています。
このように、神奈川の地で活動する企業が共に歩むこの取り組みは、持続可能な社会への道を描くための重要な一歩となることでしょう。ぜひ、ジャパンモビリティショー2025の会場で、彼らの未来への挑戦を体感してください。




トピックス(その他)

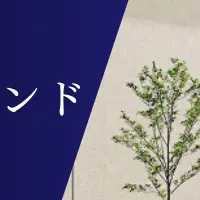




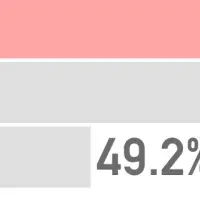

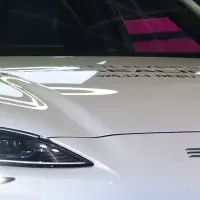

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。